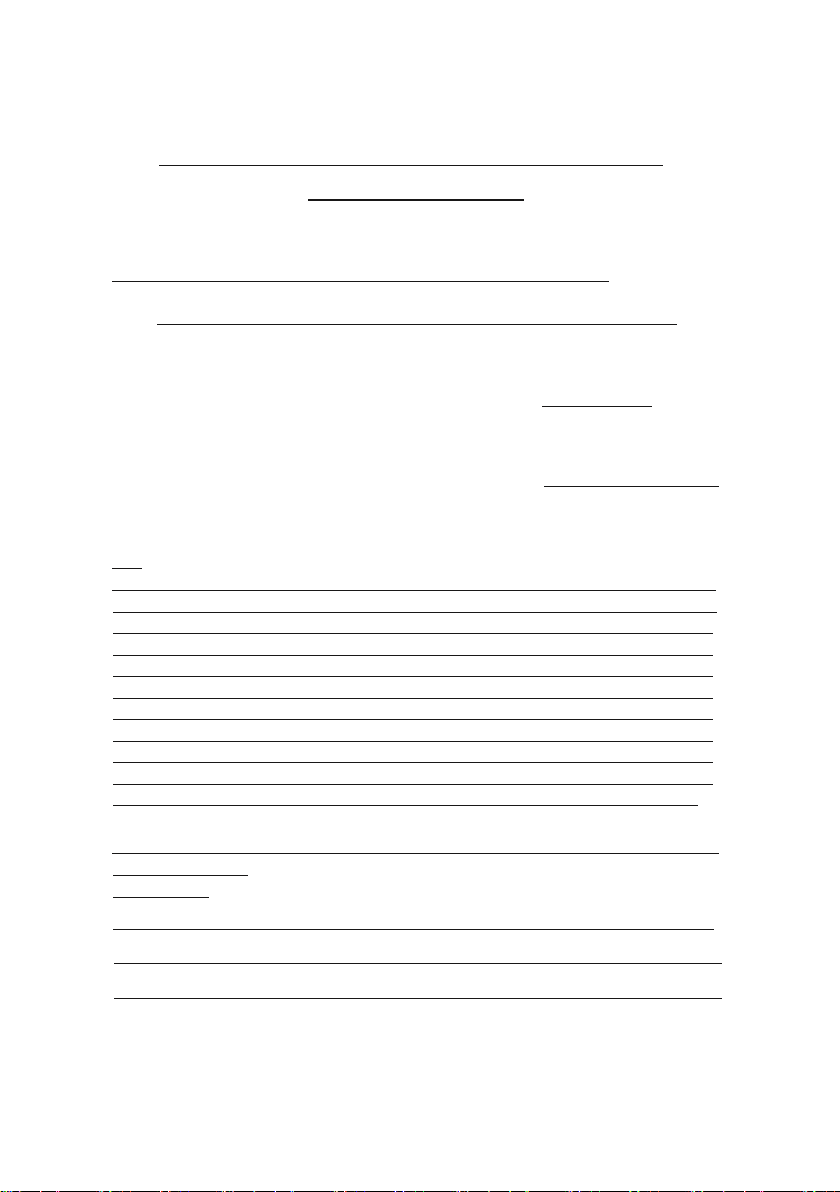
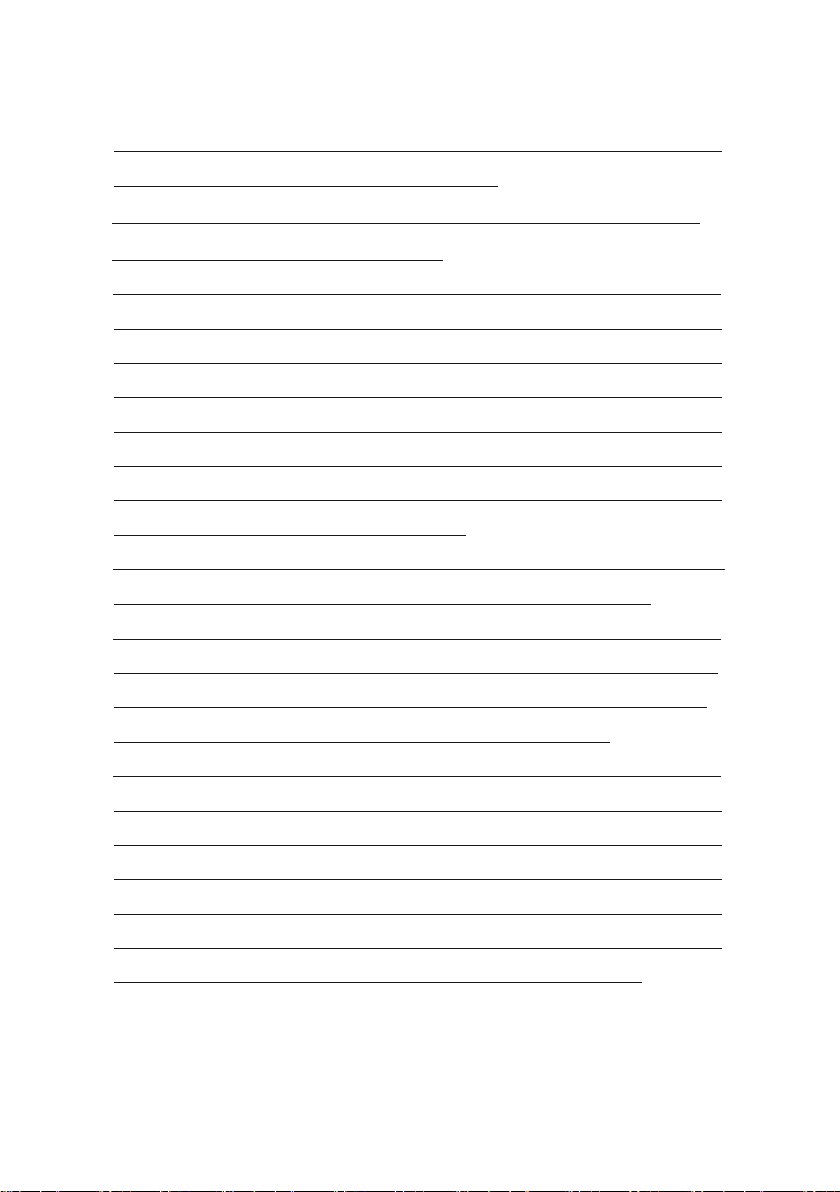
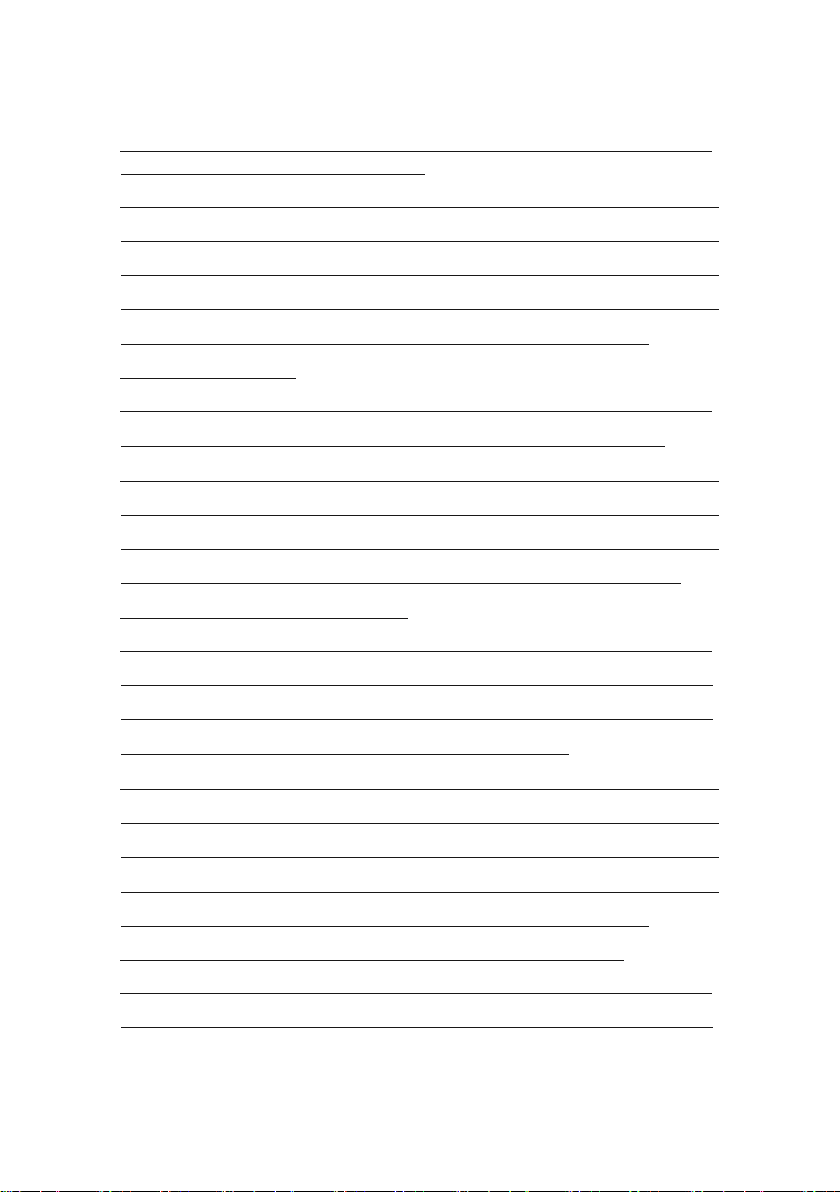
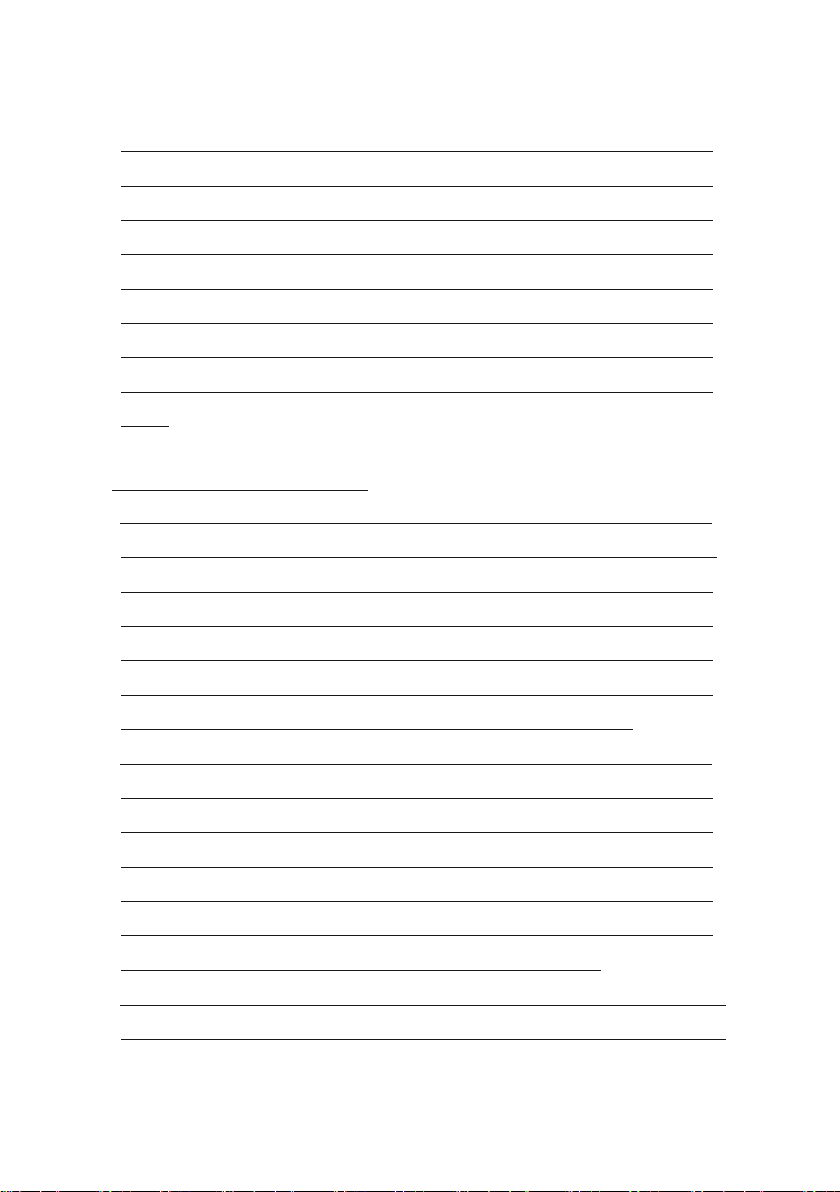
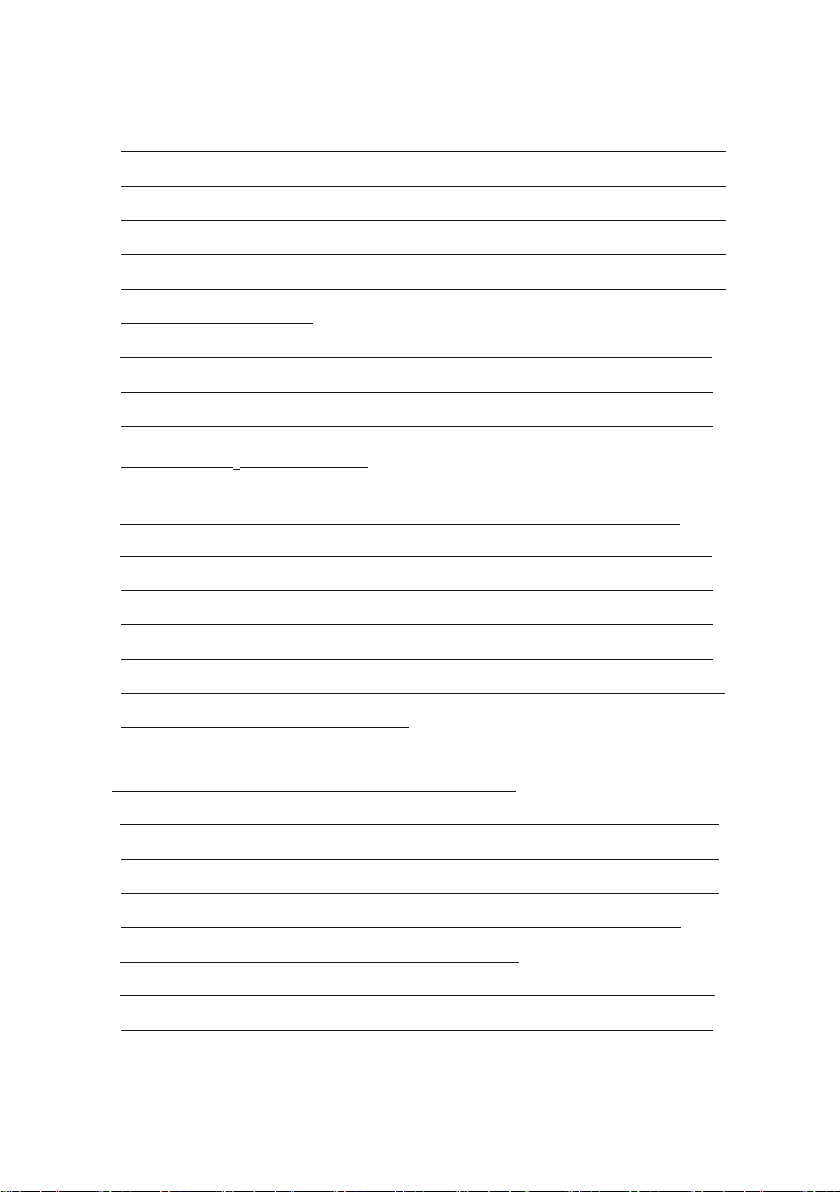
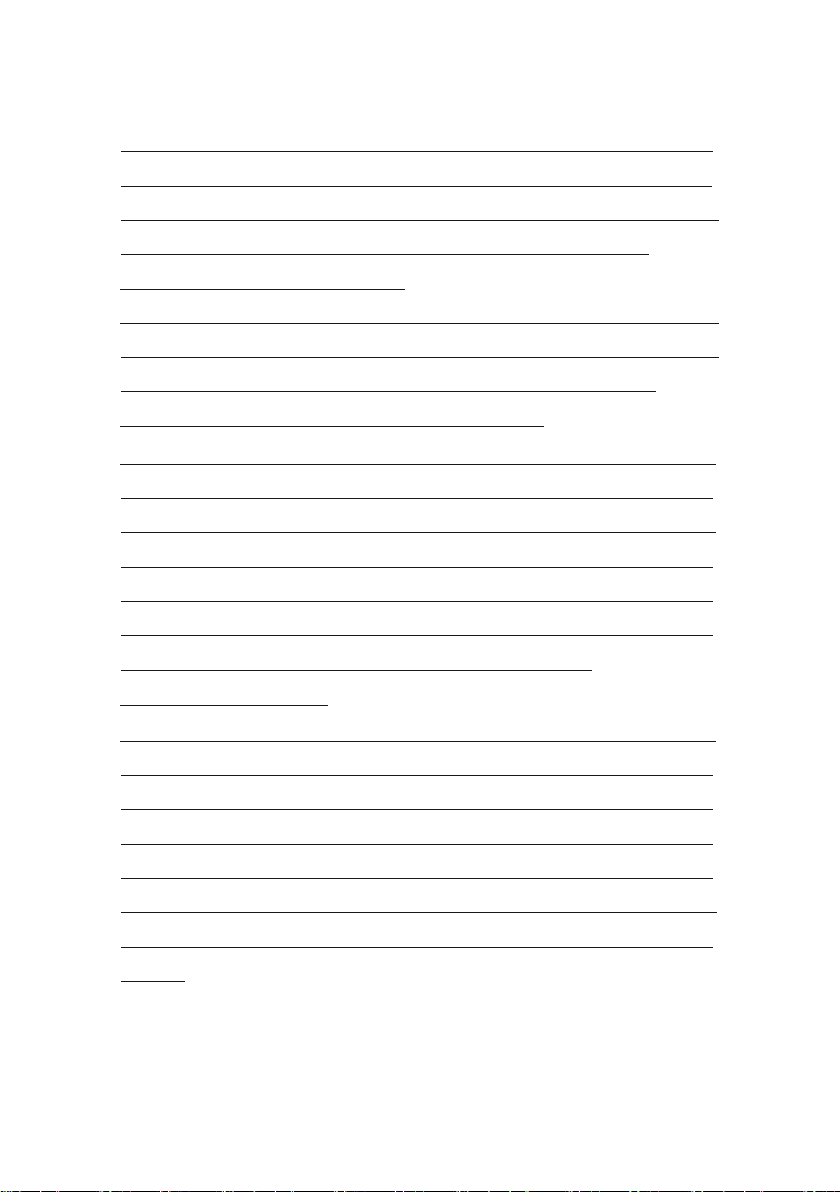
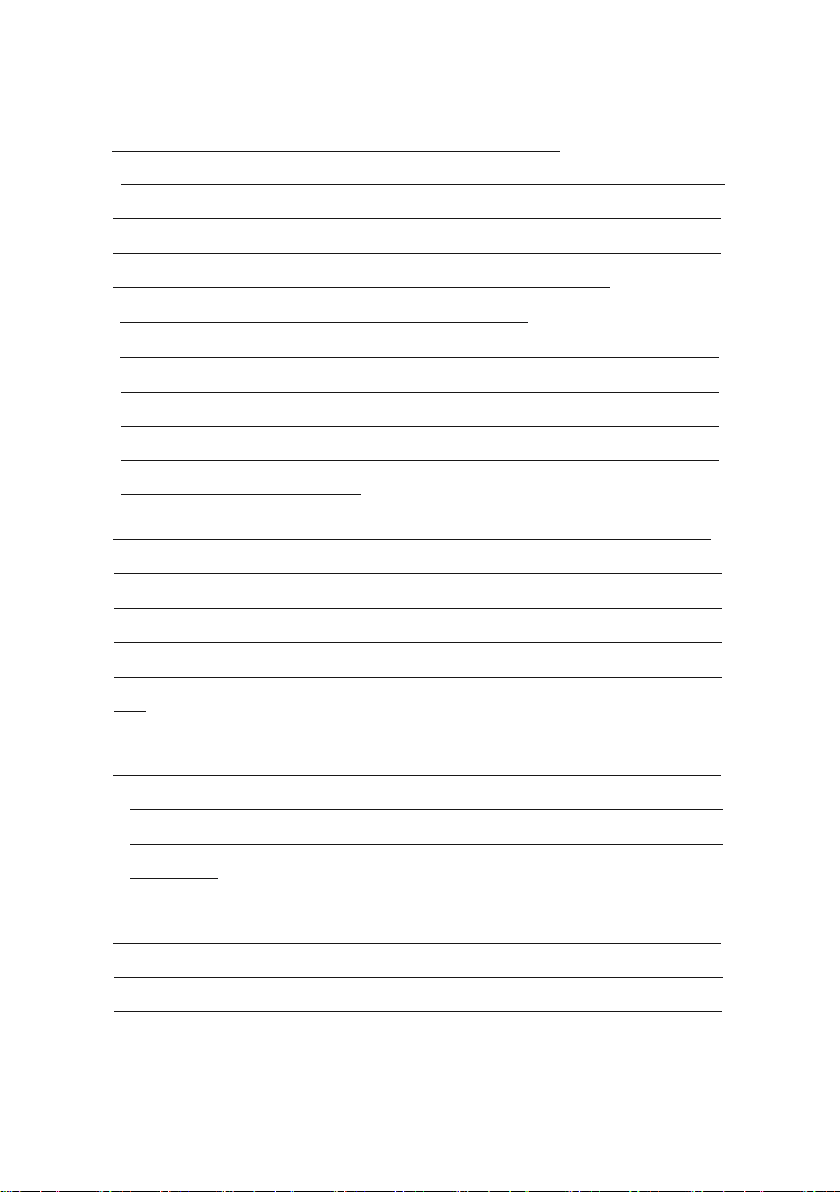
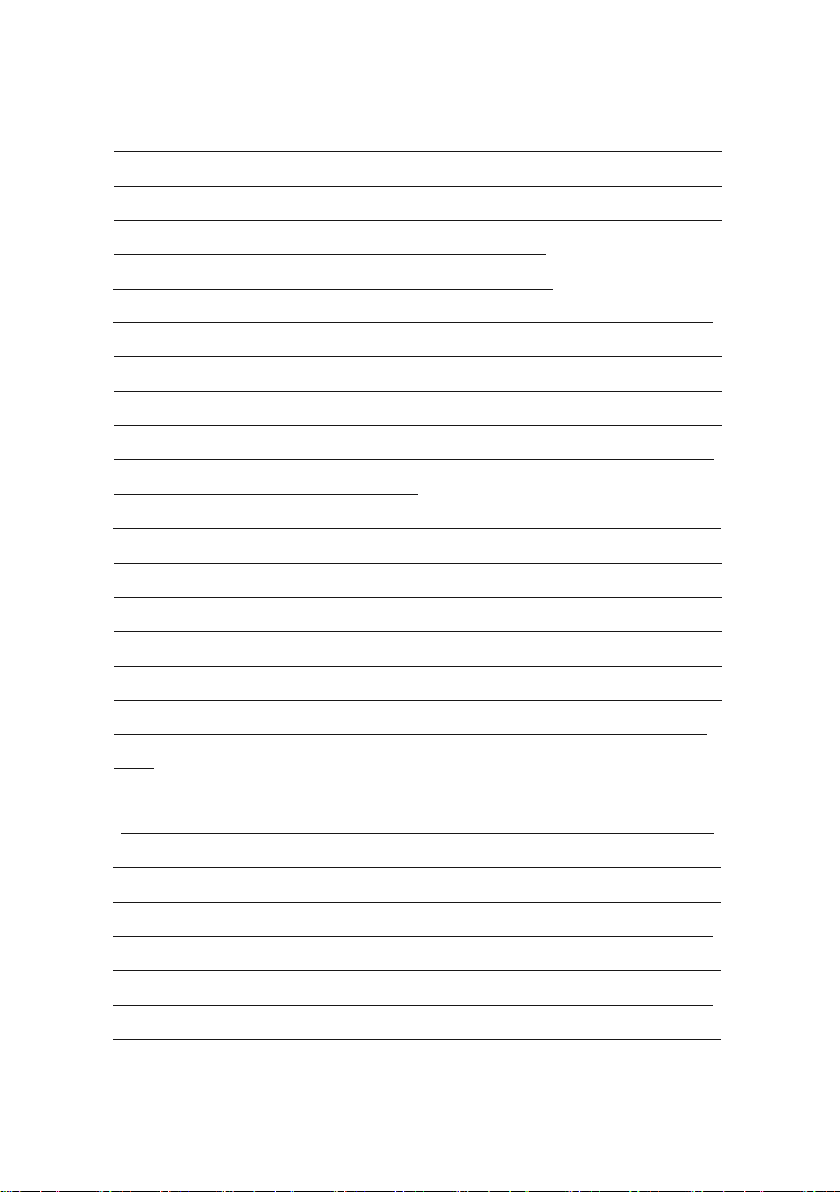
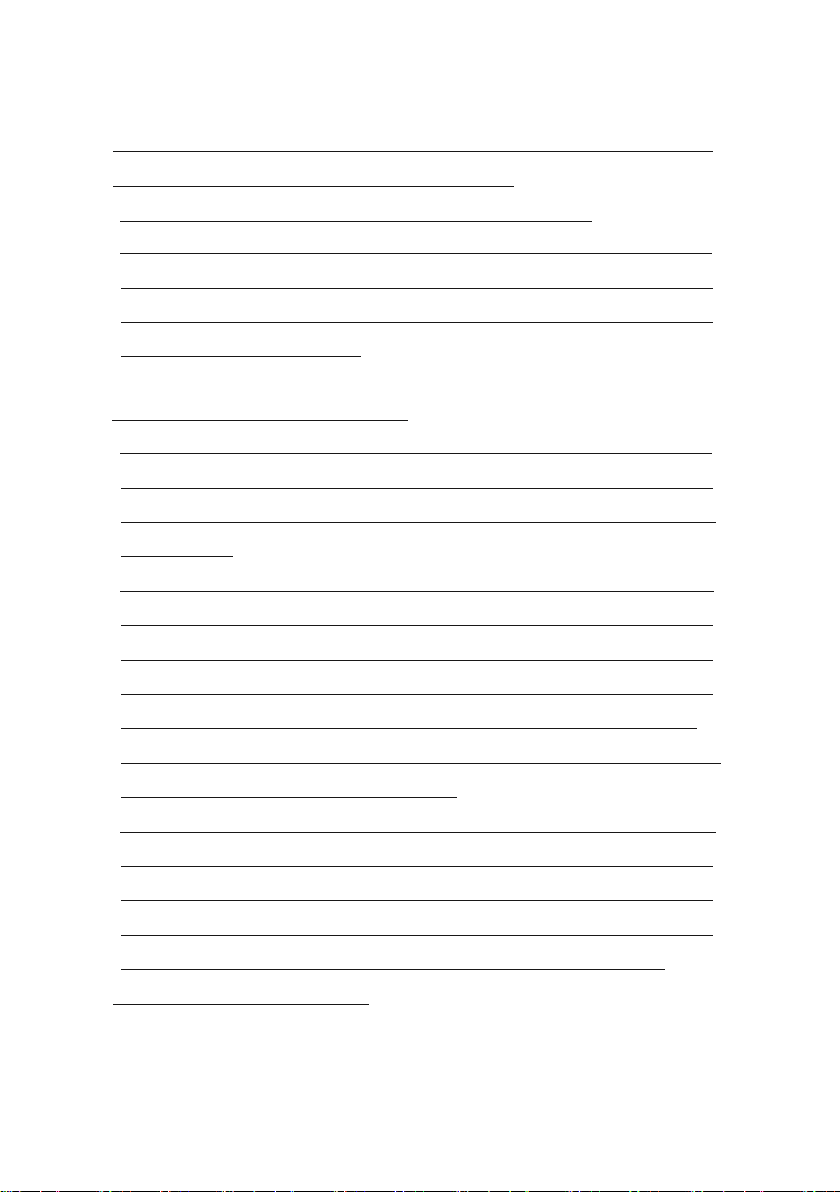
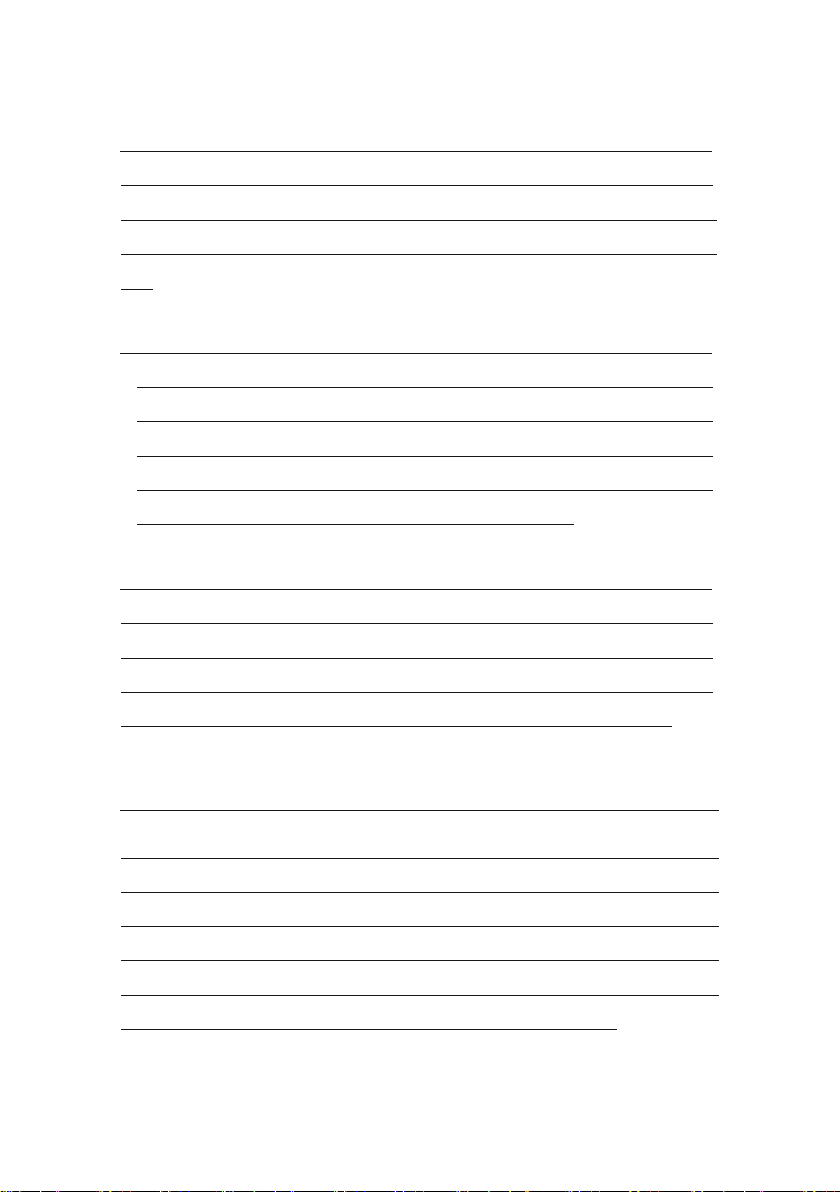
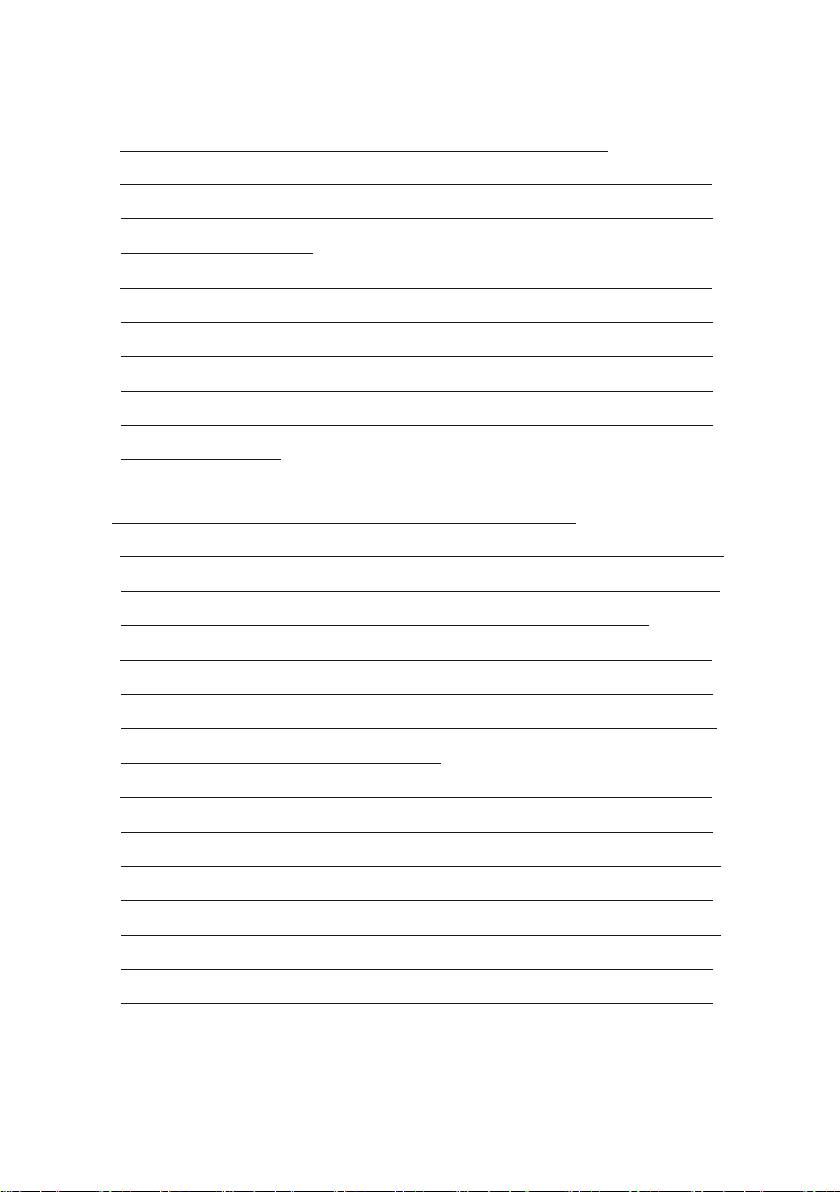
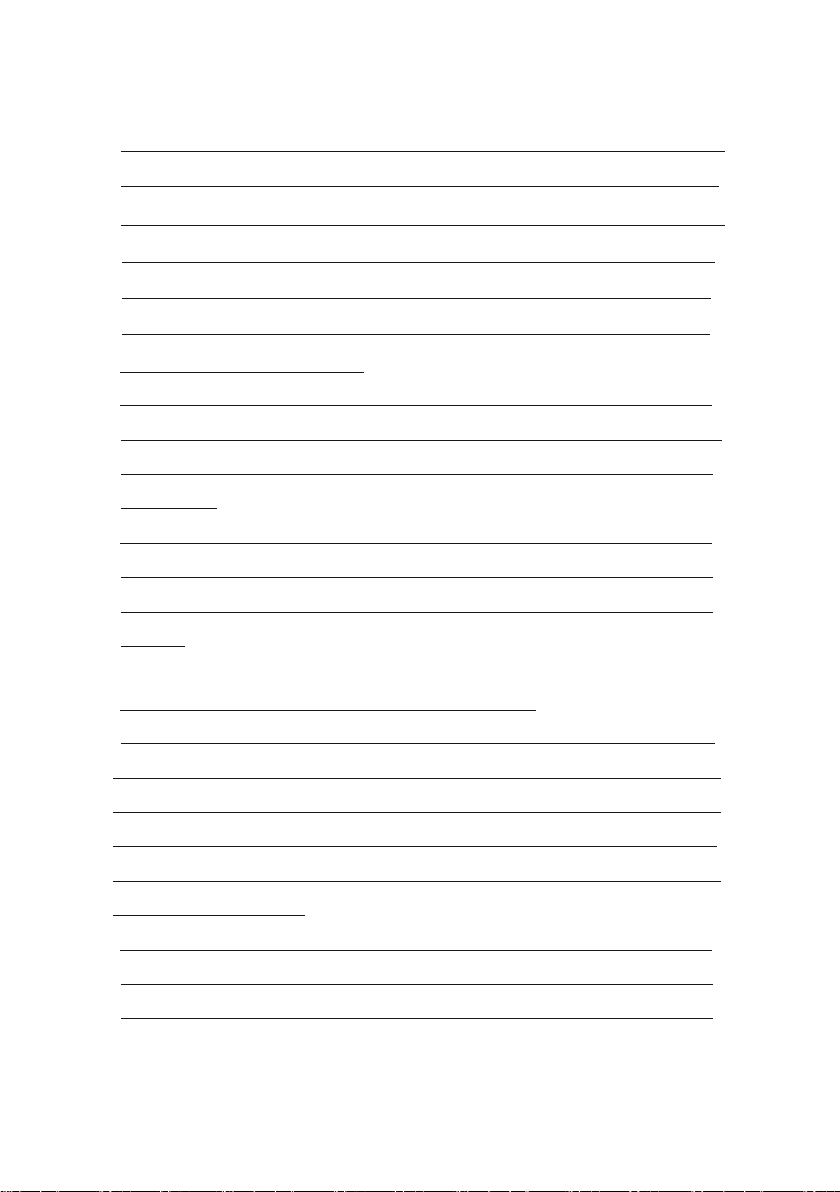
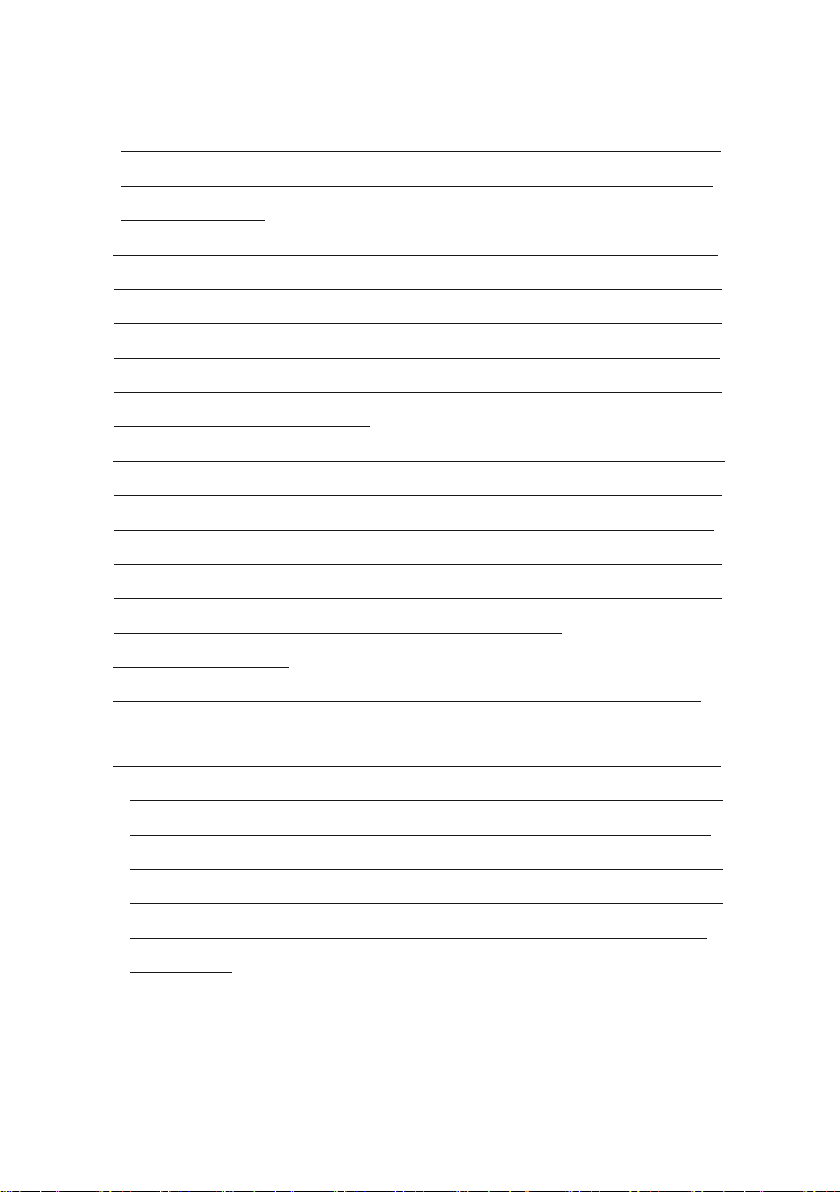
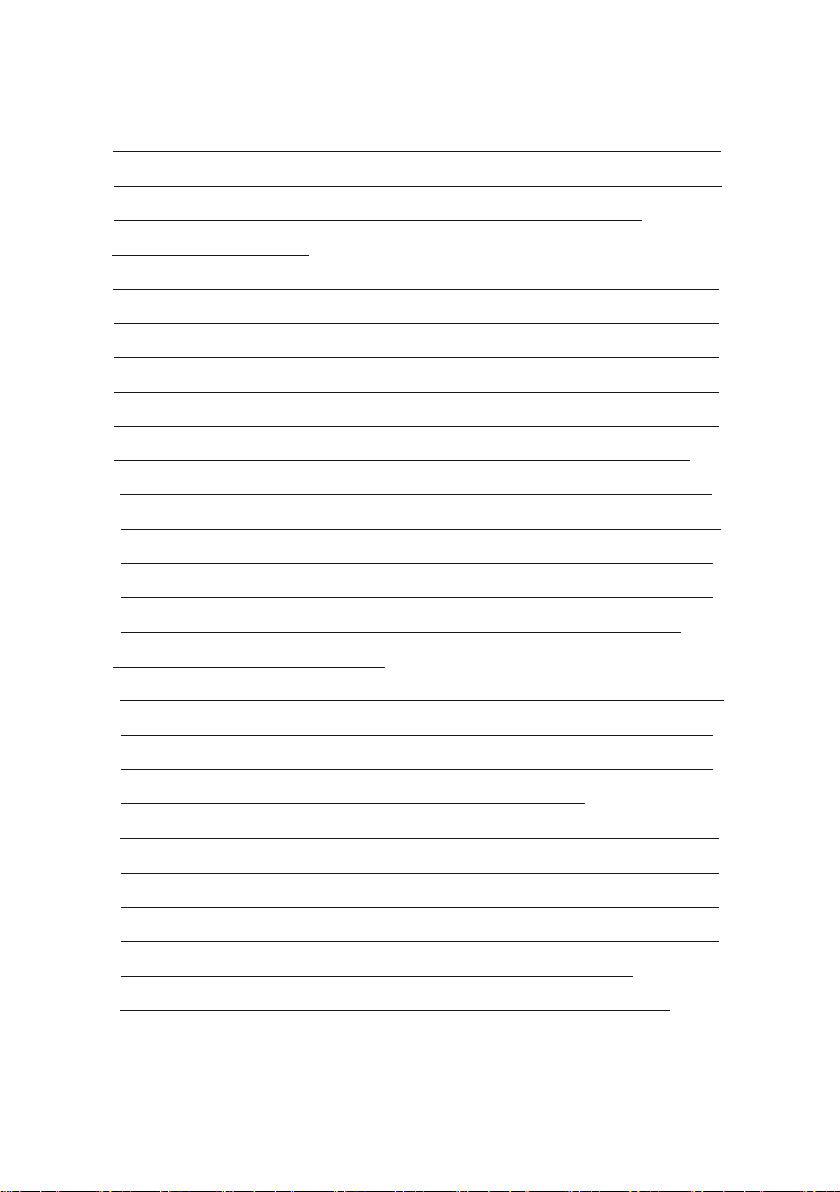
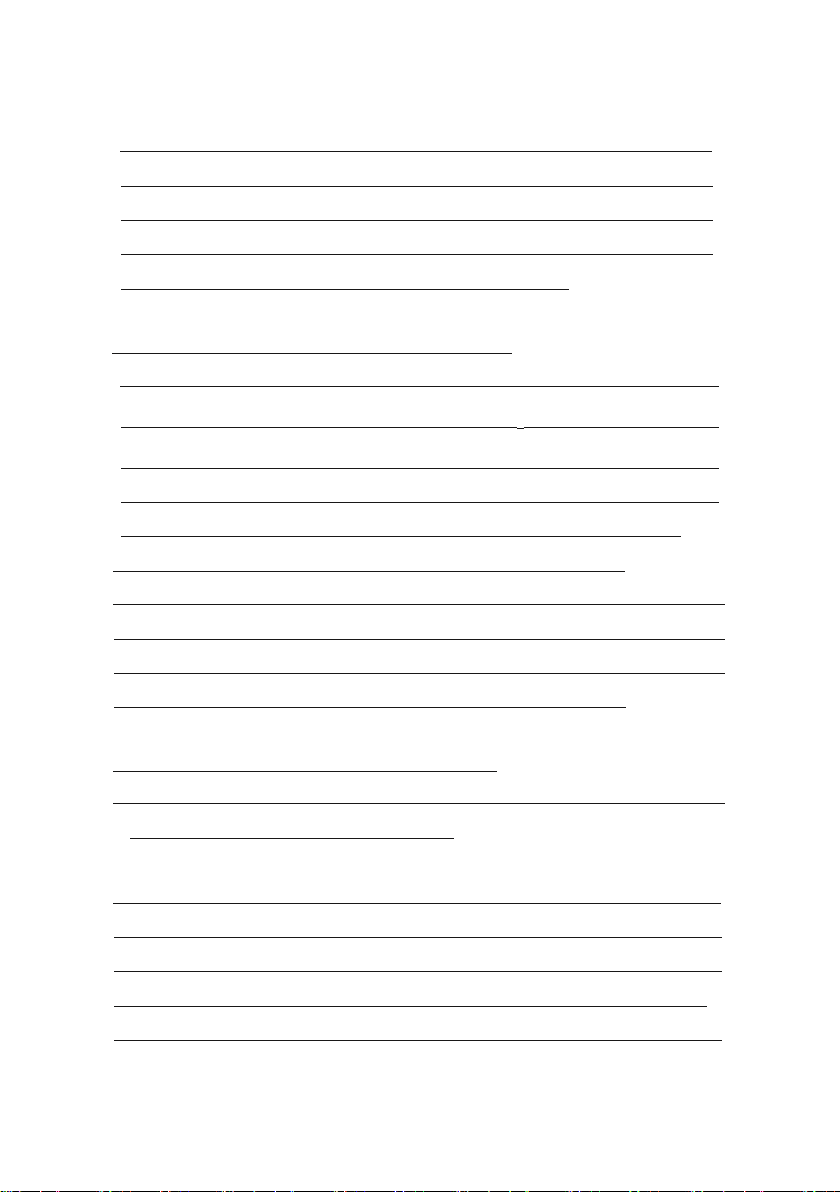
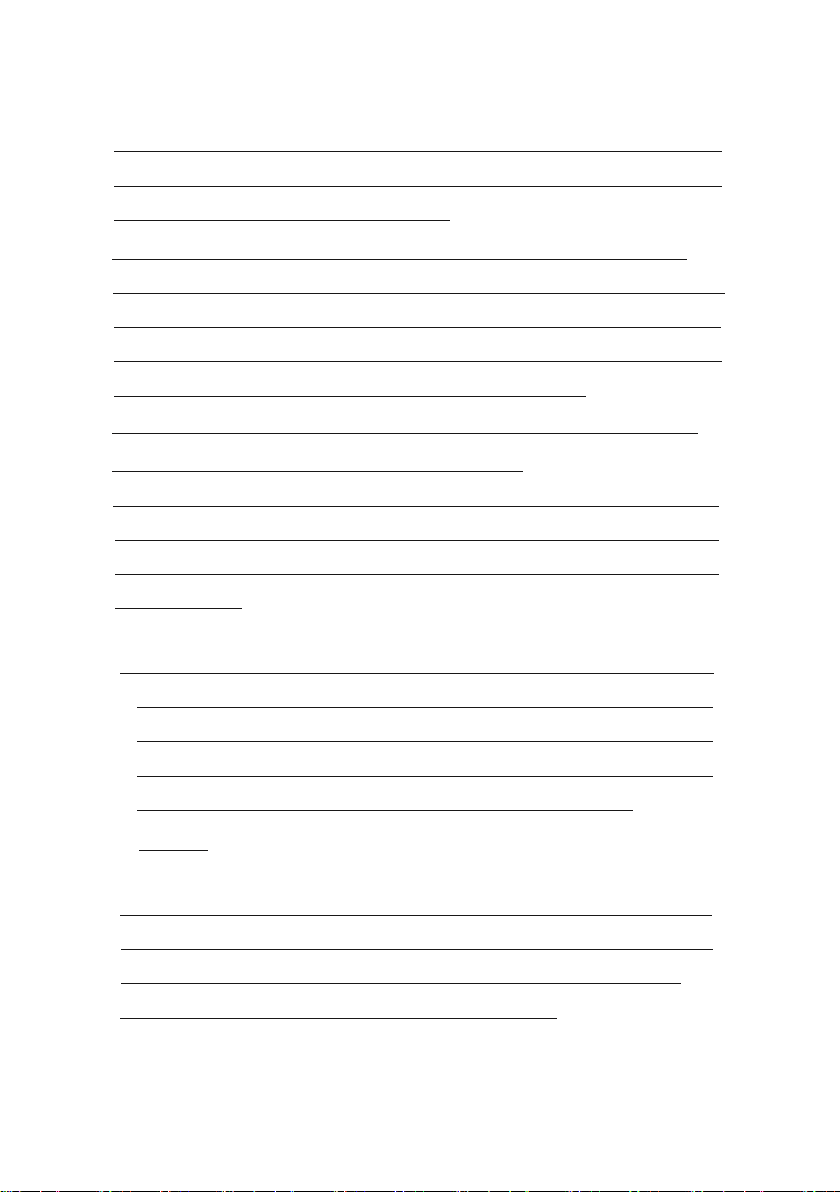
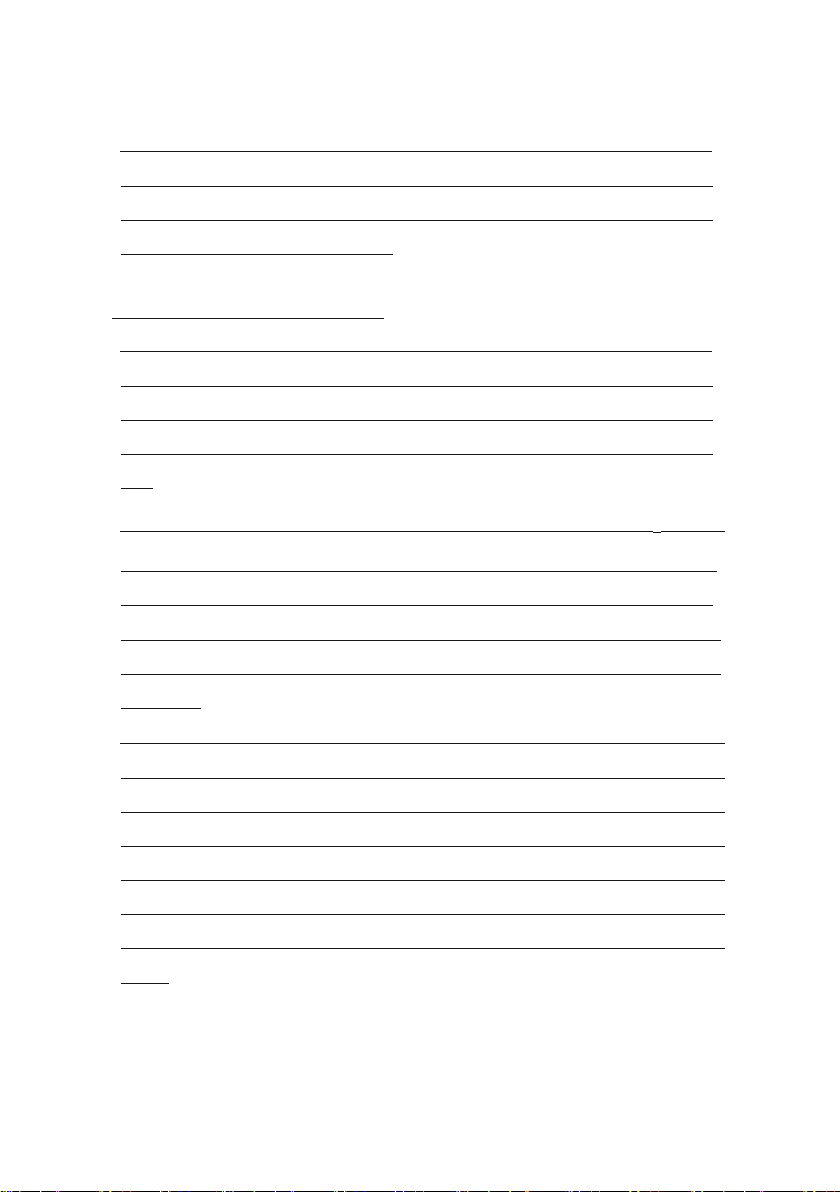
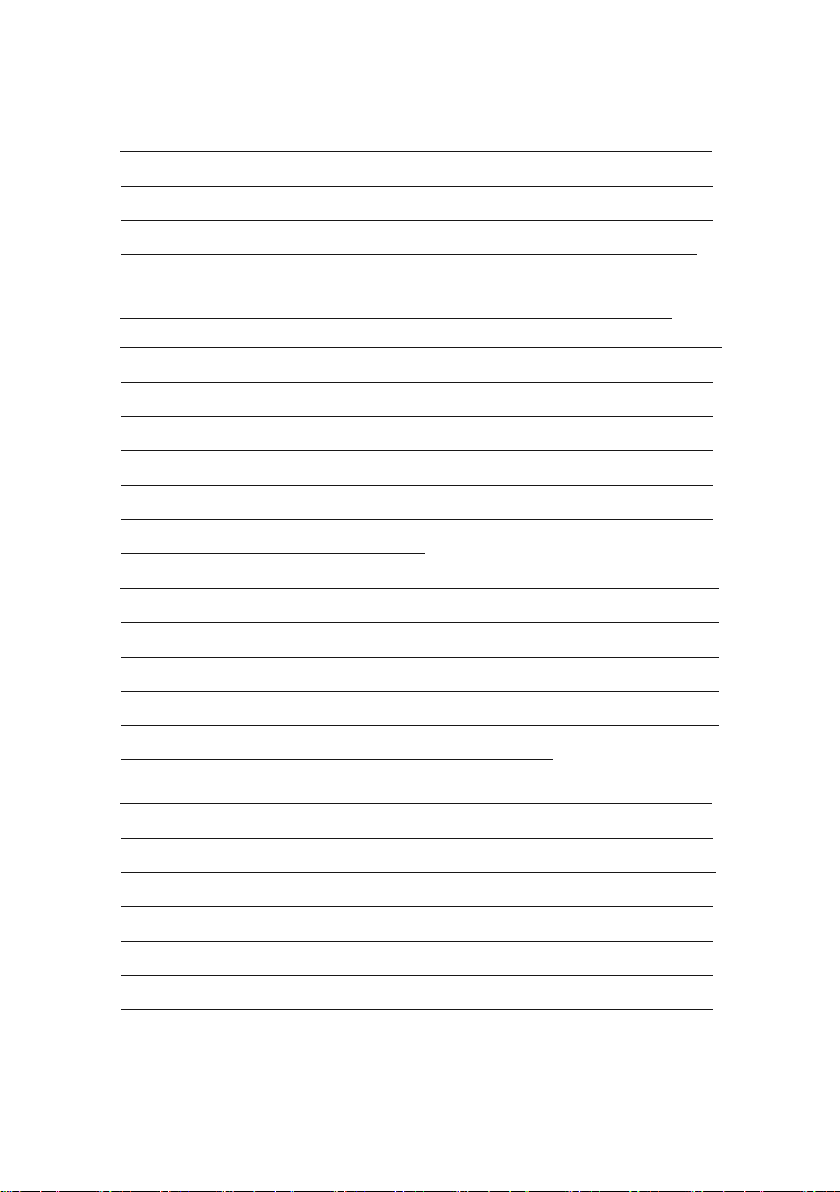
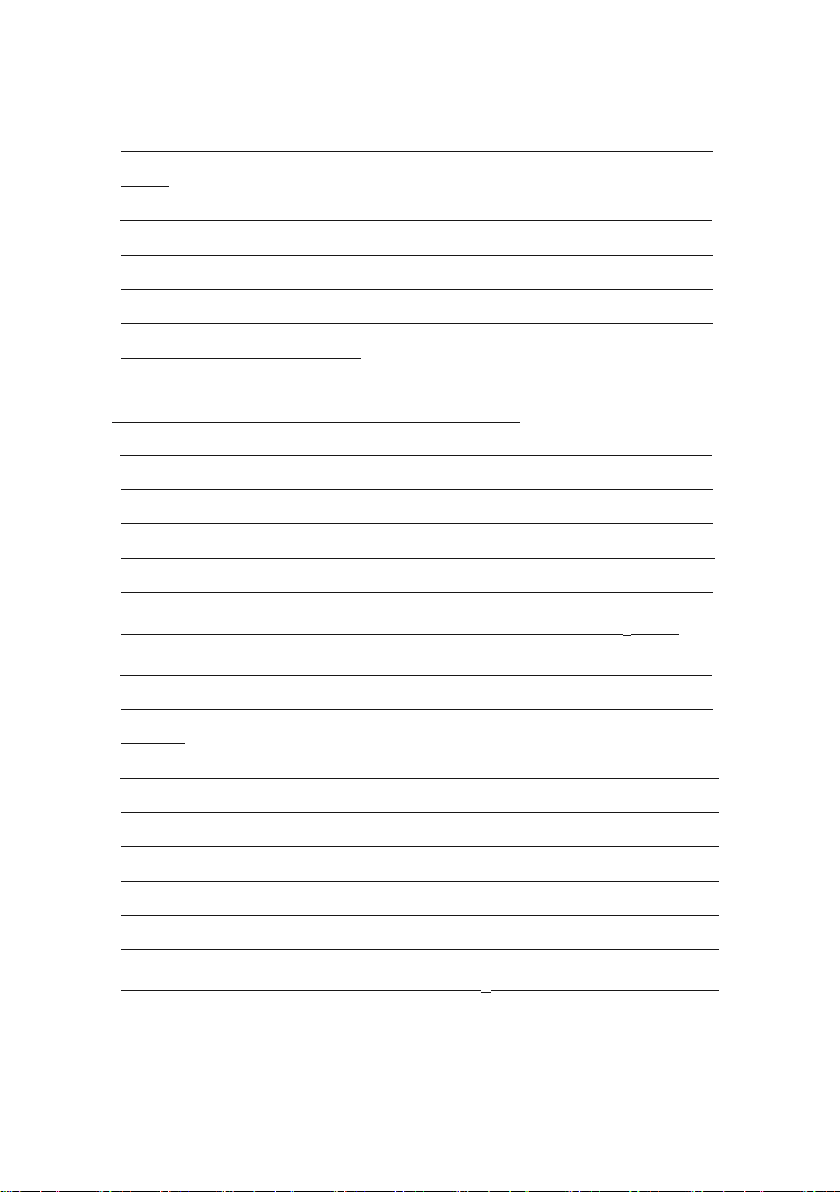
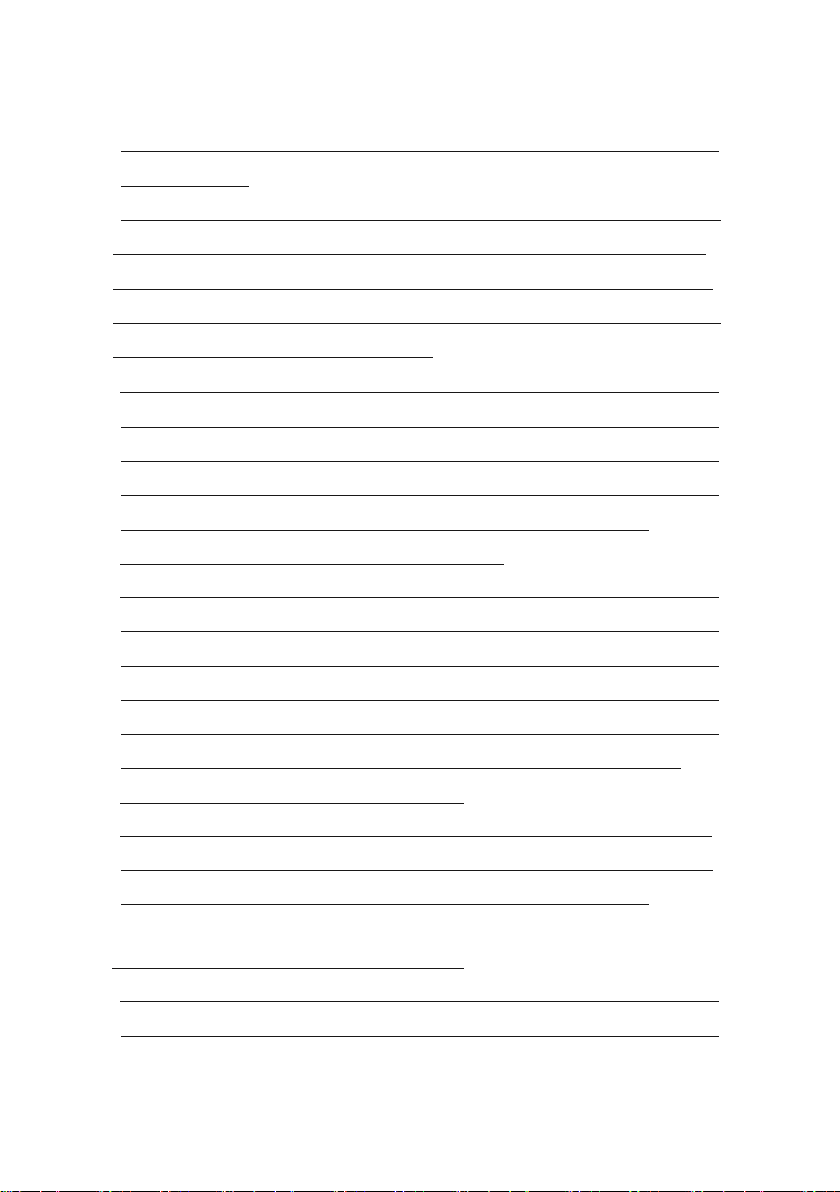
Preview text:
lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
変容するニュースキャスターの「語り」 ―重視される共感―
A Study of the Transforming News Anchor’s Speech Act:
Perspectives on the Transition to an Emphasis on Empathy 深 澤 弘 樹 Hiroki FUKASAWA 要約
本稿では、ニュースキャスターの「語る」行為に焦点を当てる。1974 年の『ニュースセ
ンター 9 時』開始以降、日本のニュースではキャスターニュースが主流となり、とっつき
やすく分かりやすいニュースがスタンダードとなった。娯楽化が進行したニュースにおい
て、キャスターは、単に原稿を読む存在から、個を表出して視聴者に社会的出来事を伝え
る重要な役割を担うことになった。本稿では、キャスターの役割の変容について、「モノ
申す」存在から共感や親密性重視への移行ととらえ、キャスター自身が著した書籍を参照
し、その存在意義や「語る」行為をどのように内面化していたのかをまとめる。それによ
り、ここ数十年間のキャスター像の変化の様態を分析した。以上により、テレビニュース
の署名性が高まるなか、彼らの役回りが、反権力を旗印に意見を述べる存在から、視聴者
の思いを代弁し共感醸成を重視した調整役に移行していること、そして、スタジオや視聴
者とのコミュニケーションを活性化する役割へと変容していることが明らかになった。
Keywords:テレビジャーナリズム、ニュースキャスター、無署名性の言語、 共感 、フレーミング機能 1.はじめに
2023 年はテレビ界の信頼を失墜させる大事件が起きた 1 年であった。ジャニーズ
問題がテレビ界を揺るがし、事実を認識していながら長らく報じなかったメディアの
姿勢が問われた。こうした事態に各局は検証番組を放送して弁明したものの、その歯 lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
切れの悪さが指摘されたほか、ジャニーズ事務所所属のタレントがキャスターを務め
ることへの批判も起き、改めてキャスターの「資格」
が問われることになった(牧野洋,『PRESIDENT Online』,https://president.jp/arti-
cles/-/74794,2024 年 1 月 8 日アクセス.)。
ニュースキャスターは放送局や番組を背負う存在であり、キャスターについて問う
ことはテレビ報道のありようを考えることでもある。筆者はこれまでニュースキャス
ターの「語る」行為に焦点を当てて、内容分析のほかインタビュー調査を通じて「語
る」ことの現状とキャスターの意識を探ってきた。研究を進めるなかで、昨今は、反
権力を掲げて自身の見解を述べる「モノ申す」タイプよりも、親しみやすさや視聴者
に寄り添う姿勢を重視するキャスターが求められる傾向があるのではないかと感じて
おり、それらは、報道に「中立・客観」を求める意識の高まりやネット社会の進展に
よる「共感社会化」が背景にあると考えている。
2011 年の東日本大震災以降、ジャーナリズムの本義とされてきた中立・客観性や権
力監視機能(ウォッチドッグ)に加えて、「ケアのジャーナリズム」(林,
2011)やパブリックジャーナリズムに基づいた「グッドネイバー(善き隣人)として
の役割」(畑仲,2014 参照)といった、受け手に寄り添う姿勢がジャーナリストに求
められるようになった。さらには、「共感報道」という言葉も生まれている(谷,
2018)。以上の流れは、キャスターのあり方にも影響を与えている。
こうした問題関心のもと、本稿では、キャスター自身や関係者が著した書籍を確認
し、キャスター自身が内面化している「理想のキャスター像」、とりわけ、「語る」
行為に対する意識と現状を明らかにする。また、実際のニュース番組におけるキャス
ターの「語り」を分析することで、現在の語り方の特徴を分析する。その際には、社
会言語学の知見を援用し、遂行的なコンテンツであるテレビニュースにおいて、コミ
ュニケーションの活性化に寄与するキャスターの役割に注目する。以上により、ニュ
ースの娯楽化のもとでのキャスターが語る行為の変容とありようを探る。 lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
2.無署名性の言語とテレビニュースにおける署名性(1)日本のジャーナリズム
における無署名性の言語とテレビの署名性
日本のジャーナリズムにおいては、明治期以降、新聞が大衆化するなかで中立性
・客観性を重視する報道姿勢が確立されてきた(有山,2008)。こうした「中立公
平・客観」報道について、言語的側面から検討した玉木明は、この理念は戦後ジャ
ーナリズムによって確立されたものとし、記者が原稿を書く場合に誰が書いたのか
がカッコにくくられ、その主体が消されることを「無署名性の言語」と表
現した(玉木,1996)。
玉木が指摘したことは、<一人称=わたし>を<一人称複数=われわれ>に引き
上げたうえで、<一人称=われわれ>を省略するという操作だった(玉木,
1996:77)。「みられる」「いわれる」に代表される受身形の表現がその例で、こ
うしたニュースの言葉では、既存の世界認知や秩序を是認し強化せざるを得ないこ
とを強調している(玉木,1996:101-102)。武田徹はこの主語の省略により、「誰
が見てもそう思うに決まっている判断を下している印象を文章が持つことにな
る」(武田,2016:189)と述べている。
では、テレビ報道の場合はどうであろうか。基本的には、テレビの報道において
も新聞原稿の作成スタイルを踏襲しており、同様の原則で原稿は作成される。ただ
し、新聞記者が紙面で記事を執筆することと決定的に異なるのは、生放送では、ニ
ュースを語る人物の「顔」が画面上に映し出される点である。
藤田真文は、稲垣吉彦(1987)の論考を参考にしながら、テレビニュースでの提
示される時間のズレに注目した(藤田,2000:191)。新聞同様にテレビニュース
の原稿は過去形で書かれるが、視聴者が見ている映像は常に現在であり、過去形の
原稿とはズレが生じる。しかし、記者が映像に登場して今まさに起きていることを
語る場合は「…しています」と現在形になり、その「語り」は「私」の明
示に結びつく。「誰が」語るかが必要だからだ(藤田,2000:192)。
画面上で視聴者に語りかけるキャスターも同様であり、現在形の語り、本稿でい
えば生放送のニュース番組では「表現者の立地点」(稲垣,1987:249)からの語り lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
が可能となる。以上のことから、テレビニュースではキャスター自身の人となりの
表出が視聴者にアピールし、その「私性」を利用して出来事を伝える特性をもつ。
ただし、玉木が指摘した「無署名性の言語」とキャスターの語りが全く関係ないわ
けではない。例えば、世論が二分されている争点でコメントする場合は、キャスタ
ーは自身の見解を述べることを避け、中立・客観を装うために「無署名性の言語」
を用いる。キャスターは、わざと「私」を消し、主語を省いて受身形にして誰が思
っているのかを曖昧にし、不特定多数の視聴者が抱くであろう思いを想定して発言
する。この場合、キャスター自身の考えはコメントの背後に隠れ表出されることは ない。
(2)キャスターの語りの不自由さ
日本の報道の伝統である中立・客観に加えて、唯一の言論立法と言われている放
送法の問題もキャスターのしゃべる内容を規定することになる。放送法第 4 条の「
番組編集準則」では、公平原則や意見が分かれている問題での多角的論点解明義務
があり、キャスターは自身の意見を述べることに慎重となる傾向がある。この法律
は放送局側の倫理的ガイドラインとする説が学説的には定説であるが(山田,2016
)、過去には不適切な放送に権力側が介入した経緯もあり、問題を起こすことをた
めらう放送局側の政府への忖度が問題視されたこともあった(後述)。
放送局所属のキャスターが政治的なトピックで何らかの意見表明をすることは難
しく、昨今は局アナ以外に複数のコメンテーターをスタジオに配して意見を聞くス
タイルが一般化したのもそのような理由があるからであろう。また、東日本大震災
では地震や原発など、専門性の高いトピックでの語りも求められることになったが
、それも容易ではない。コメンテーターである専門家に質問を振ることが多くなり
、キャスター自身が専門性を身につけることの限界もあってキャスターがあらゆる
分野において専門的見地から語ることは実際には不可能といえる。
そうした制約があるにせよ、番組がキャスターに負う部分は大きい。キー局のニ
ュースでは新たなキャスターが誕生する際には記者発表が行われ、世間の注目を集 lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
める存在であることから、アナウンサー・キャスターのタレント化・キャラクター
化も進行している。毎年、「好きなアナウンサーランキング」が発表されたり、会
社員であるアナウンサーの私生活がネットニュースを通じて報じられることからも
、人々の関心度が高いことがわかる。局の顔として、彼ら / 彼女らの知名度を生か
して視聴率につなげたいとの思惑も局側にはあり、番組としての浮沈をキャスター
が握っている部分もある。
したがって、中立や客観が重視される日本のジャーナリズムの伝統や放送法との
整合性の問題のほか、局の顔としていかに振る舞うべきかといった様々な葛藤をキ
ャスターは抱えているのであり、そうした意識は筆者の調査でも明らかになってい
る(深澤,2015a,2016,2018)。
3.キャスターは語る行為をどうとらえていたのか―資料から見えてくるもの
ニュースキャスターは中立・客観性の要請と局を背負う看板としての個の表出と
の狭間にいる。こうした相克は、キャスターニュースの発展によって顕著になった
ものであり、「誰が」キャスターを務めるのか、キャスターが「何を」語るのかが
注目されるようになったことが背景にある。本章では、キャスターニュースが発展
した 1970 代以降のキャスター自身がその役割をどう捉えていたのかを過去の文献等
の資料をたどることで明らかにしたい。
(1)NHK『ニュースセンター9 時』磯村尚徳の言葉から
日本の本格的なキャスターニュースの歴史は 1962 年に TBS の『JNN ニュースコ
ープ』から始まったとされるが、キャスターニュースを定着させたのは、1974 年 4
月 1 日にスタートした NHK の『ニュースセンター9 時』である。この番組は「視聴
者にアピールする分かりやすいワイドニュース番組を」の方針のもと制作され
たものであった(NHK 放送文化研究所,2002:223)。
キャスターを務めた磯村尚徳は、『NHK 報道の 50 年』のなかで、「普通の人の
、普通の言葉で話をしたい」との思いをもってしゃべり、アナウンサーからは「プ lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
ロの話し方ではなく、茶の間の人の話し方」だと批判を受けたことを明かしている
。ただし、これは狙ったことであったと磯村は言う(
「NHK 報道の記録」刊行委員
会,1988:393-394)。生放送でのセールスポイントは磯村自身のアドリブであり、
前もって打ち合わせのできない性質であると『続ちょっとキザですが』の
なかで述べている(磯村,1977:221)。
キャスターが「語る」行為は NHK 局内だけでなく一般的にも当初は受け入れら
れず、番組スタートと同時に多くの視聴者から「NHK ニュースらしからぬ」と苦情
の電話が相次いだそうだ(
「NHK 報道の記録」刊行委員会,1988:379)。
しかし、その後、風向きが変化し視聴率は二けたに乗る 1。
こうして市民権を得た『ニュースセンター 9 時』であるが、先述の「無署名性」
に関連して述べると、キャスターの容姿が画面上に現れることによって、キャスタ
ーの署名性が前面に出ることになる。『NHK 報道の 50 年』のなかで、磯村が番組
に関する質問に答えている箇所がある。「そうした方法論、演出論が同時にテレビ
放送での署名性への傾斜を、促していったわけですね」との質問に対して磯村は、
「テレビというメディアでは、伝え手の存在自体が一つの情報なんで、嫌でも署名
的要素が強いということです」(
「NHK 報道の記録」刊行委員会,
1988:397)と答えている 2。
以上のように、『ニュースセンター 9 時』における磯村の登場は、ニュースにお
いて「原稿を間違わずに読む」という従来のアナウンサー像を一変させ、キャスタ
ーのメディア性を浮かび上がらせ、テレビニュースの「署名性」を高めることにな
った。この点について、田中孝宜は「それまで透明な媒介者に過ぎなかったキャス
ターの人称化を際立たせ」
(田中,2018:132)ることになったと述べている。この
ように、『ニュースセンター 9 時』の登場は、テレビニュース界にとってはエポッ
クメイキング的な出来事であり、その後のキャスターニュースの道筋を示すことに なった。 lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
(2)テレビ朝日『ニュースステーション』久米宏の言葉から
娯楽化の流れをさらに加速させたのが、テレビ朝日で 1985 年にスタートした『ニ
ュースステーション』の久米宏キャスターの登場であった。古田尚輝はこの番組を「
キャスターニュースを極端にまで追及した先見的でかつ論議の多い番組」としたうえ
で、特徴の一つとして「久米宏の個性・技量・経験に依存する度合い
の高い番組」であったと指摘する 3(古田,2011:32)。
アナウンサー出身の久米は番組内で個人的な感想や信条を述べ、それが視聴者の
共感を得る一方で、反発と批判も引き起こした。では、当の久米自身はいかなる考
えのもとで番組を担当していたのであろうか。以下、久米が 2017 年に著した『久
米です。』 から引用してみたい。 久米が大切にしたのは、「話し言葉でニュー
スを読む」ことであった(久米,
2017:203-204)。原稿には手を入れ、紋切り型の表現はより平易なものに手直しし
たことが語られている。言葉の語順や接続詞の使い方にも気を配り、慣用句を使わな
いよう心掛けた。それは「生きた言葉」を話すためであり、原稿の下読みは黙読で本
番で初めて声を出して読むようにし、新鮮さを重視した。また、カメラ目線で原稿を
読むことができるプロンプターも使わなかったという。その理由を以下のように述べ る。
古臭く見えてもかまわない。たまに手元の原稿に目を落としながら「あのー、次
はですね」と伝えたほうが、人間味があって親しみやすい。立て板に水のような読
みは聞きやすいかもしれないが、不思議なことに言葉が伝わらないのだ。(久米, 2017:208)
また、「オリジナルを最優先したコメント」を重視し、「誰に相談することもなく
、それを独断で実行した」
(久米,2017:214)という。さらには、「僕は自分の感覚
を最も信用していた。その自信は自分がいちばん視聴者に近い視点に立っているとい lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
う思いに裏打ちされていた。もし自分の感覚がずれてきていたら、そのときは番組を
辞めるときだと考えていた」とも述べ、自身のコメントの判断基準は視聴者の感覚で
あり、自信をもって発信していたことを明かす。そして、久米が最も優先したことは
、「まだ誰も言っていないことを言う」、そして「誰も考え
ていない視点を打ち出すこと」だった(久米,2017:215)。
さらには、失言も演出であり、「コメントがニュースの見方を変える」 「これまで
の見方、みんなと同じような意見を発すれば視聴者に伝わるという思い込みは、コメ
ントの発信者が陥りがちな最大の落とし穴だ。たとえ最大公約数の意見とは違っても
、僕は『そういう考え方もあるな』と思える見方をできる限り提供しようと努めた」
(久米,2017:216)と述べ、無難な発言に終始しないようオリジナルの言葉を紡ぎ
出そうと努力していたことがうかがえる。
この番組は、娯楽化が進行するテレビニュースにおいて、外部のプロダククション
が初めて手掛けたことも特徴的であるが、久米の発言からは、とりわけ「見せる」工
夫が施されていたことが分かる。また、以下のようにも述べている。 キャスター
やアナウンサーではなく、一人の人間として番組の中に存在する。ニュースに対する
コメントも、一人の人間としてどう考えるかを言葉にする。そんなふうに出演者たち
が番組の中で「人間として生きている」と感じることができる。いってみれば、僕は
ニュース番組にストーリーのあるドラマを持ち込みたかったのだ。(久米,2017: 220)
以上の言葉から、ニュース番組であっても様々な演出面を重視していたことがう
かがえるが、単に視聴者の興味を惹くことが重要ではなく、ジャーナリズムに重要な
ウォッチドッグ機能も重視していたことは以下の言葉から明確だ。久米は「メディア
の役割は権力のチェック」であり、「『公正・中立』なニュース番組などあり得ない
。なかでも政治ニュースを公正・中立に伝えることは不可能だ。取り上げるニュース
を取捨選択する段階で、すでに公正を逸脱しているのだ」としたうえで、「 『政府が
することは何でも批判しよう』というくらいの気持ち」でいて、「当時の政権は自民 lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
党だったため、番組のスタンスは結果的にアンチ自民党になった」 「それは政権の座
にあるからであり、それ以外に理由はない」とも述べ、
自覚的に反権力を貫いていたと語っている(久米,2017:236)。
この言葉からは、久米自身に政治的な強い信念があっての発言というよりも「演
出としての反権力」ともとれ、論争を巻き起こすがための演出と考えられなくもな
いが、久米は「素人の感覚」を大切にし、反権力を久米なりの洒脱な言葉で語るこ
とで一時代を築くことになった。
(3)TBS『NEWS23』筑紫哲也の言葉から
『ニュースステーション』の成功は、ニュース戦争を引き起こすことになる。そ
うしたなか、1980 年代から 90 年代にかけて久米と双璧を成したのが、朝日新聞記
者からニュースキャスターに転身し TBS『NEWS23』のキャスターに就任した筑紫 哲也であった。
筑紫哲也の起用については、TBS で筑紫の薫陶を受けた金平茂紀がいきさつを書
籍で記している。金平によると、『ニュースステーション』に対抗する形で、久米
宏に太刀打ちできる人物として白羽の矢が立ったのが朝日新聞記者の筑紫哲也だっ
た(金平,2021)。では、筑紫はキャスターとして、どのようなスタンスだったの
であろうか。筑紫の著書『ニュースキャスター』から紹介していく。この番組は
1989 年 10 月 2 日にスタートしている。およそ 2 カ月間のわずかな準備期間を経て
の開始だったという(筑紫,2002:17,22)。
本書第 5 章に、「キャスターの仕事とは何なのか」を筑紫が語る箇所がある。筑
紫はアメリカの例を出しながら、日本の場合は、今一つ「キャスターとは何か」が
判然としないとし、「アメリカの場合は、まずジャーナリストであること、その経
験を経ていることを最低限の資格要件とする考え方もあるが、私たちの国ではそう
でない人がむしろ立派にその役をこなしているのを見ると、これも怪しい」
(筑紫,2002:87)と書いている。 lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
筑紫はキャスターについて、明確な定義づけをしていない。ただし、著書から筑
紫の考えを垣間見ることはできる。同書 156 頁では、2001 年 10 月 24 日付朝刊の
『毎日新聞』の「21 世紀の日本のオピニオンリーダー」という世論調査で筑紫自身
が 4 位に入ったことを受けて、オピニオンリーダーについて以下のように述べてい る。
オピニオンリーダーとは「世論形成」に力がある人、方向を示す人のことだろ
う。だが自分がそうだという実感が私にはほとんどない。むしろ逆の思いをする
ことが多い。ジャーナリストと呼ばれる仕事を始めてから、世論や世の中が「こ
うあるべきだ」と私が思ったり、主張する方向に動いたことはまずない。ほとん
どの問題について、私の発言やその表現の手法には、自分が「少数派」であると
いう前提、自覚の下でやってきた。(筑紫,2002:156-157)
以上のように、筑紫には、オピニオンリーダーとして社会をある一定の方向に導
こうとする意図や自覚はなく、あくまで世論や主流派の逆側にあえて立つことを是
としていることが分かる。そうした考え方のもとで、筑紫が手掛けたのは「テレビ
にコラム欄を作ってみようという提案」であった。それが「多事総論」というコー
ナーとして結実する。毎日 90 秒間の一人しゃべりで構成されていた(筑紫, 2002:160)。
このコーナ ーでは、「もっと番組としての特色、アクセントを強め、できれば 旗幟を鮮明にしたい」
(筑紫,2002:161)との意図があった。それに対して、批判
的な人がいたとしてもそれを引き受ける覚悟をもってのスタートであった。筑紫は
「オピニオンらしきものを言う以上、それに反対、批判的な人がいるのは当然であ
る。当の発言者(私)が世論に逆らう少数意見になりがちならなおさらのことであ
る」と世論におもねらない態度を貫く覚悟をもっての発言であることを示し、「明
確に私という個人のフィルターを通した『ひとつの見方』だと断った lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
ほうがフェアで正直だと思う」と述べている(筑紫,2002:169)。
以上のように、テレビ報道であっても番組全体として客観的に伝えることを「よ
し」とせず、テレビ番組で「オピニオン」を提示し、社会への問題提起しようとし
ていたことが見てとれる。
ここまで、かつてのニュース番組における代表的人物のキャスター対する考え方
を紹介した。アナウンサー出身の久米と新聞記者出身の筑紫では、そのバックボー
ンが異なることから、自ずとのその表現の仕方には違いがある。ただし、共通して
いたのは、社会の主流の考え方や世論におもねらず、あえて少数派の立場を貫こう
と考えていた点だ。中立公平が求められるテレビ報道でその態度を体現しようとし
たのが彼らであった。
(4)ニュース戦争その後―政権との関係とネット社会の進展―
磯村キャスターが『ニュースセンター 9 時』を担当してから 2024 年で 50 年が経
過しようとしている。久米キャスターが番組を退いてから 20 年となる。この間、政
治権力とテレビ報道をめぐって安倍政権時代には重要な出来事があった。
古舘伊知郎、国谷裕子、岸井成格ら各局を代表するキャスターが相次いで降板す
る事態が 2016 年 4 月の改編期に起きた。彼らは政権側に批判的な発言をしており
、安倍政権下での放送法第 4 条を盾にしたテレビ局への圧力、テレビ局側の忖度が
噂されたが、実情は明らかになっていない。
こうした動きに対して、山田健太は、政府の「介入」を通じ、「番組の善し悪し
は時の為政者が判断する、という社会ルールが定着しかけている」と厳しく指摘し
た(山田,2016:7)。山田はさらに、番組の偏向に対して「それは悪いことだとの
見方が社会に風潮として定着しつつある」との認識が一般化しているとも述べてい
る(山田,2016:8)。こうした現状を、山田は権力監視の弱体化ととらえる(山田
,2021)。 日本の報道の自由度が脅かされていることは「国境なき記者団」が発
表した「報道の自由度」ランキングにおいて日本が下位に低迷していることにも示 lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
されている。2023 年 5 月のランキングで日本は前年に比べて 3 ランクアップしたも
のの 68 位にとどまっている。これは G7 で最下位である(Reporters without Borders
HP,2023 PRESS FREEDOM INDEX,https://rsf.org/en/index,2024 年 1 月 7 日アクセ
ス.)。その理由として、記者クラブの閉鎖性のほか、安倍政権下のキャスター降
板とそれ以降の「忖度」による報道の萎縮への懸念が挙げられている(柴山哲也 ,
朝日新聞社「論座」,https://webronza.asahi.com/national/articles/2022050900002.html,
2023 年 9 月 19 日アクセス.)。
さらには、ネット社会においては、テレビ出演者の発言はすぐにネットニュース
で取り上げられたり SNS で拡散される傾向にあり、その発言は番組内にとどまらな
い。このような状況を考えればキャスターが自由に発言することの困難さは容易に 想像できる。
こうした言論状況の変化のなかで、キャスターたちはいかなるスタンスでニュー
スに向き合っているのであろうか。現役のニュースキャスターたちは「伝える」こ
とに対していかなる考えを持っているのかを、同じく書物やネット記事から見てい きたい。
4.現役キャスターの言葉から(1)大越健介のスタンス
まずは、NHK での『ニュースウオッチ 9』(2010 年~ 2015 年 ) 担当後、2021 年
秋から『報道ステーション』キャスターを務める大越健介に注目する。彼はもともと
記者であり、アナウンサーではないためしゃべりのプロではない。そのため、考え方
は同じく記者出身の筑紫に近いところがある。彼が 2012 年に著した『ニュースキャ
スター』を読むと、何よりも現場での取材を大事にして、そこで感じた思いを言葉に
託していることが分かる。
キャスターの役割については、「私のコメントは、それを際だたせ、あるいはも
う一度解きほぐすものでありたい。『そのニュース、核心はどこだ。』という旗を
立てて、視聴者の皆さんの確かな水先案内人になることが、最終表現者としてのキ lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
ャスターの仕事だと思っている」
(大越,2012:74)と「確かな水先案内人」という
表現を使って、自身がニュースの核心に迫り、それを視聴者に伝えるガイド役であ ることを強調する。
また、本稿のテーマである VTR の前後の語り(コメント)についても言及してい
る箇所がある。大越は、項目の前の「前説」、後ろの「後説」と呼ばれるコメントの
作成が最も大切な仕事だと言い、その大切さは、「ニュースの輪郭をしっかりと描き
出す『仕上げ』の役割を負うからだ」(大越,2012:46-47)という。そのために、「
ニュースの制作段階からいろいろと関与し、その本質を理解するのは自分の責務だ」
(大越,2012:47)と述べている。
また、大越はニュースではアドリブで語る場合もあると述べる。それは「VTR を視
聴者とともにじっくりと味わい、視聴者の目線でトークをする方がよい場合もあるか らだ」
(大越,2012:47)としたうえで、「キャスターはしゃべる機械ではない。プ
ライバシーを守りつつも、人間としての生き方や価値観、時には個人的な事情もにじ
み出た方が視聴者との距離も縮まるというものだ」(大越,2012: 48)と述べ、アド
リブを用いた進行による視聴者との一体感の醸成に期待を寄せ
る(大越,2012:50)。
そして、67 頁の「『自分のことば』でニュースを語る」では以下のように語る。
長い間、記者として取材者の立場にあった私は、磯村さんがそうであったように
、自分のことばで語らなければならない。もちろん、ニュースに対し、安易に私見
を加えることは絶対にあってはならない。しかし、20 年以上にわたって記者を務
め、取材を積み重ねてきた自分の個性は、何らかの形でにじみ出る。ならば、それ
をしっかりとした自覚のもとでコントロールして、視聴者にメッセージを発する方
がいい。それがキャスター就任に当たって自分に課した宿題であった。(大越, 2012:67-68) lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
以上のように「最終表現者」としてのキャスターの役割を位置づける。ただし、大
越がコメントに託す思いは、「私憤ではなく公憤」である。語る際には「私憤を越え
て、多くの視聴者と共有するに値する公憤であるという確信」が求められ
る(大越,2012:69-70)。
さらには、公共放送・NHK の政治的公平性に関して、「野放図に私見を垂れ流す
報道はもちろん許されない。しかし、そのことと、評価を避け、ひたすら道のまん
中をおそるおそる歩くようにすることは同じではない」(大越,2012:70-71)とす
る。この発言は、NHK に所属している頃の発言であるが、中立が求められる放送、
そのなかでも民放に比べて厳格なルールが課せられている NHK においても、取材に
基づいたうえでのオピニオンはある程度許容する立場であることがうかがえる。
そうしたなかで、キャスターとは「放送という巨大な媒体の怖さを正しく認識し
、抑制的にニュースの見方を示すジャーナリストである」(大越,2012:10)とし、
「私は単なる伝達者であろうとは思わない。未熟であっても、時代が求めるメッセ
ージを自分なりに感じ、考え抜き、発信し続ける存在でありたい。その大前提とし
て、今の世の中に生きるまっとうな常識人でなければならないと思っている」
(大越,2012:10)とも述べている。
このほか、「行動するキャスター」(大越 ,2012:235)でありたいと表現し、当事
者たちと会い、現場から「生きた言葉」を紡ぎだしたいと決意を述べる。大越が声
高に意見を述べるのではなく、「抑制的にニュースの見方を示す」姿勢を強調する
ことからも、あくまで軸足は視聴者側にあることがうかがえる。
さらには、2015 年刊行の『もの言うキャスター』巻末の池上彰との対談において
、キャスターの仕事とは、「共感」を生み出す仕事と位置づけている。ニュースの
「受け」において、時には何も言わないことも必要で、視聴者のリズムを考えるべ
きと大越は言う。それに対して、池上は「視聴者代表」としての重要性を説き、生
身の人間として伝えること、十分な判断材料を提供して、あとは視聴者
に判断してもらうことが大切なのだと述べている(大越,2015:280-283)。 lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
こうした考え方は視聴者に寄り添う姿勢から来るもので、先に述べたケアのジャ
ーナリズムや課題解決型ジャーナリズムにも通じる。これらは公正性、共通善を求
めるもので大越の姿勢はそれを体現しようとするものである。書籍のタイトルは「
もの言う」となっているが、その「もの言い」は個人的な見解ではなく、地道な取
材に裏打ちされて得た人々の思いの代弁であるといってよい。
(2)コロナ禍で注目された藤井貴彦キャスターの発言
キャスターが共感を重視する姿勢は筆者が地方局のキャスターを対象に行ったイ
ンタビュー調査でも明らかになっており(深澤,2015a,2017,2018)、先述した
ジャーナリズムの新たな潮流に対応するものだ。コロナ禍で日本テレビの藤井貴彦
キャスターのコメントが称賛されたこともその流れとみてよいであろう。ここでは
、藤井キャスターの発言を紹介し、注目された理由を探るとともに、藤井キャ
スターの著書を通して昨今のキャスターが内面化している意識に迫る。
コロナ禍で日本中が苦しんでいるなか、『news every.』(月曜~金曜:1 部 午後 3 時
50 分~、2 部 午後 4 時 50 分~、3 部 午後 5 時 53 分~午後 7 時)の藤井キャスター
の発言が注目を集めた。2020 年 4 月 27 日の『マイナビニュース』掲載の木村隆志の
コラムによると、藤井アナは、ニュース内で以下のような発言をした。
命より大切な食事会、パーティはございません。
感染者数に一喜一憂しないでください。この数字は 2 週間前の結果です。私たち
は 2 週間後の未来は変えることができます。
藤井アナは 2020 年には好きなアナウンサーランキングで 3 位に入り、高感度の高
いアナウンサー、キャスターとして知られている。コラムニストの木村は、会社員と
してのアナウンサーの微妙な立ち位置を人気の秘密に挙げた。これは有名人でありな
がら会社員であることで、この微妙なポジションが緊急時には「みなさんと同じ 1
人の会社員としてメッセージを伝える」ことにつながっているという。このほか、当 lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
時のコロナ禍という特殊事情も関係していると木村はみる。不安をあおる映像、コメ
ントが多いなかで藤井キャスターの言葉が希望を感じさせてくれた点も理由として挙
げている(木村隆志,『マイナビニュース』,
https://news.mynavi.jp/article/20200427-every_fujii/,2024 年 1 月 4 日アクセス)。
なお、藤井キャスターは 2023 年のランキングでは首位となり、2021 年以来 2 度目
の首位を獲得している。『ORICON NEWS』によると、好きな理由として「視聴者に 寄り添っている」「
「アナウンサーとしての制約がある中でも、自身の想いを伝えてく
れる信頼できるアナウンサーさん」とのコメントが見られる( 「第
19 回好きな男性アナウンサーランキング」『ORICON NEWS』,https://www.oricon.
co.jp/special//65828/#link1,2024 年 1 月 8 日アクセス.)
こうした視聴者に寄り添い、一緒になって泣き笑う姿勢は、藤井自身が著した書
籍から、言葉の使い手としての哲学、思いを感じ取ることができる。2021 年の著書
『伝える準備』のなかに、お笑いのボケと突っ込みについて書いた箇所があり、こ んな表現がある。
SNS の世界では批判や中傷が飛び交い、言葉の使われ方がとても冷たくなって
います。誰かを支えたり、励ましたり、喜ばせたりすることに言葉が使われたら
、日常はもっと素敵になるでしょう。……後ろ向きな言葉を前向きに換えるって
少し難しいけど、楽しい。言葉を少し変換するだけで、人を笑わせるほどのエネ
ルギーや相手を納得させるパワーが生まれてきます。(藤井,2021: 172-173)
このように、藤井は前向きであたたかい言葉の効用を強調する。また、「批判す
ることよりも励ましたい」とし、「見栄えのいい言葉だけが届くのではなくて、鋭
い批判だけが力を持つのではなくて、相手を頭に思い浮かべた言葉こそが届く
のだと信じています」と述べている(藤井,2021:183-184) lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
こうした表現からは、藤井自身がキャスターを務めるうえでのスタンスを垣間見
ることができる。藤井キャスターの発言から見えてくるキャスターの姿は、「切れ
味鋭く」権力を批判する反権力型というよりも、視聴者に寄り添いその思いを掬い
取って代弁するキャスター像である。
(3)社会の変化とキャスターの言葉
以上から確認できたのは、現在のキャスターが共感を大切にする姿勢であり、視
聴者と同じ視点、目線で語り等身大のナチュラルな姿をさりげなく画面上で提示す
る姿である。こうしたキャスターの姿は、時代の変化に伴うものであり、久米や筑
紫が鮮明にしていた「反権力」を表明することを嫌う世の風潮も背景にはあるだろ う。
2000 年代以降、日本の保守化、右傾化が議論されてきた(田辺編,2019; 小熊・樋
口編,2020) 。このうち、マス・メディアの報道に関連して、林香里と田中瑛はネ
ット時代のテレビについて、政治的公平性の規則に縛られるとともに、「広告収入
の減少のなか、内容はリスクを回避した平準化、陳腐化へと向かっている」(林・田
中,2020:129)と指摘し、市場原理が働くなかでの伝統的メディアの右傾化を指摘 している。
受け手についても、保守化が進み権力監視を重視しない傾向も浮かび上がる。新
聞通信調査会が毎年行っている「メディアに関する全国世論調査」では、新聞の信
頼度の変化について聞いている。そのなかで、第 16 回の 2023 年調査では、「新聞
の信頼感が低くなった理由」として「特定の勢力に偏った報道をしているから」が
49.4%で前年度よりも 4.6 ポイント上昇している(新聞通信調査会「第 16 回メディ
ア に 関 す る 全 国 世 論 調 査 」 ,https://www.chosakai.gr.jp/wp/wp-content/themes/
shinbun/asset/pdf/project/notification/yoron2023houkoku.pdf,2024 年 1 月 8 日アクセス .)。 lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
これは新聞に対するものであるが、旗幟を鮮明にすることに対して好ましくない
と思っている人の増加がうかがえる。こうした風潮とキャスターの語りの変化を安
易に結びつけることには慎重でなくてはならないが、ネット社会の進展と相まって
社会の変化もまたキャスターのありように影響を及ぼしているといえるだろう。
5.キャスターの語りの「現在」
(1)ニュースの遂行性のなかのキャスター
昨今のニュース番組はオフジャンル化 4 が進行し、情報番組と見分けがつかなくな
っており、キャスターのほかにコメンテーターを配し、多数の出演者がスタジオ内
でトークする様子が頻繁に見られる。その場合にキャスターは自身の意見を述べる
よりも出演者に質問し、内容を要約する役回りを担うことになる。こうした場合、
キャスターが担う働きをどう考えればいいのであろうか。ここでは、テレビニュー
スの性格を「遂行性」の観点からまとめている藤田真文の議論を補助線として、ニ
ュースキャスターの役割を考えてみたい。
藤田は、テレビニュースにおける「物語」性に着目し、同じ題材を扱ったとして
も、その物語の濃淡には差異が生じることを明らかにした。その物語はテレビニュ
ースにおける編集によって生成されるものであり、藤田は、広義の編集と狭義の編
集に分けて論じた。とりわけ、取材した映像を編集して音声や CG を加えるなどの
狭義の編集ではなく、ニュース全体をある一定の価値意識のもとでまとめあげる「
広義の編集」の観点から分析を試みている(藤田,2008)。
藤田は、テレビニュースとは原稿を読むアナウンサーや現場からの記者レポート
、取材映像などが放送時点で組み合わされ、まとまりのあるニュース項目に仕立て
上げられる遂行的(performative)な映像コンテンツであることを指摘している(藤
田,2008:68)。この場合、生放送を仕切るのはキャスターであり、キャスターは
原稿を読むだけでなく、時にアドリブを交えながら発言したり、スタジオ内ではコ
メンテーターやゲストに質問するなど、昨今の大人数化が進むスタジオ展開におい
て、キャスターの仕事量は増加する傾向にある。つまり、遂行的なコンテンツであ lOMoAR cPSD| 58778885
駒澤社会学研究 62 号 2024 年
るテレビニュースのコミュニケーションを活性化させているのがキャスターなので ある。
この場合、磯村や久米時代のようにメインキャスターがあるトピックについてカ
メラ目線で個人的な見解を述べることに加えて、遂行性の高い生放送のニュース番
組においては、キャスターはスタジオ内で多数の出演者のコミュニケーションの仲
立ちを担い、同時に画面の向こうの視聴者に分かりやすくニュースの内容を伝える
ことにも力を尽くすことになる。 (2)
「コミュニケーションの活性化」を担うキャスター
昨今のキャスターは自身の意見、感想を述べるにとどまらず、スタジオ内を仕切
る役割を担っている。その作業はニュースにおいて、当該トピックをどう解釈する
のかというフレーミングの働きを担う。この点について社会言語学の知見を用いて
考えていく。まず、フレーミングとは Gitlin によると、「シンボルを扱う人が、言
葉であれ映像であれ言説を規則的に組織化する際に依拠する認識、解釈、提示の持
続的パターン、選択、強調、排除の持続的パターン」
(Gitlin,1980:7; 烏谷,
2001:79)を意味する。メディア組織はニュース内で、出来事を意味づけ、フレー
ミング(枠づけ)をしているのであり、キャスターが語るコメントも同様の役割を 果たす。
村松賢一は、ニュース後のコメントの働きについて、視聴者にニュースの受け止
め方(解釈=フレーム)を示しているとして、フレーミング機能を有するものと結
論づけている(村松,2005:13)。Entman によると、フレーミングの本質とは選別
(selection)と際立たせ(salience) であり、具体的には、出来事に対する①「問題の
定義」(problem definition)、②「原因の解釈」(causal interpretation)、③「道義的
評価」(moral evaluation)、④「解決策の提案」(treatment recommendation)にかか
わる表現がその機能を果たす(Entman,1993:52; 村松,2005:14)。この考え方 lOMoAR cPSD| 58778885
Komazawa Journal of Sociology No.62,2024
を援用すると、スタジオ内でのキャスターの役割は、出来事の解釈、評価、提案を 行うことである。
このほか、社会言語学者の Gumperz は、発話を解釈する際に、解釈の枠組みであ
るコンテクストはお互いの相互行為によって生み出される側面に着目した(岩田,
2022:183)。スタジオ内での相互行為を促す役割を担っているのが現在のキャスタ
ーであり、自らの発話のほか、ゲストとの会話などの資源を用いて、コミュニケーシ
ョンを活性化させフレームを形作っていく。
コミュニケ―ションの活性化については、テレビ討論の司会者の役割を分析した
本田厚子の論考が参考になる(本田,2004)。本田は、討論の司会者が「中立的立
場」を維持して進行管理役に徹しながら、いかに討論の活性化の役割を担っている
のかを分析した 5。本田は、先行話者の発言を要約したり解説を加える行為を「パ
ラフレージング」行為としており、議論の展開や先行話者の発言を分かり
やすく再呈示する役割を果たす(本田,2004:72)。
また、司会者が特定のスタンスから特定の見解を支持する場面がみられることを
例に出し、それは議論活性化の戦略であるとし、進行役である司会者には中立の立
場からの司会進行と見解を述べることの相矛盾する役割が同時に求められているこ
とを指摘する(本田,2004:73)。こうした自身の見解を述べる行為を本田は「司
会者の『中立的立場放棄』行為」と呼ぶ(本田,2004:77)。この行為は、「中立
的立場を維持した上で行われる司会者の一連の行為と等しく、討論の秩序形成
に寄与している」(本田,2004:87)といえる。
キャスターとテレビ討論の司会者を同一視はできない。しかし、昨今のテレビニ
ュースは情報番組との区別がつきにくくなっている。特にコメンテーターを配する
場合は司会の役割の比重が大きくなっているといえるのではなかろうか。
(3)スタジオ内におけるキャスターの振る舞い
続いては、2023 年 12 月に放送されたニュース番組を題材にして、これまで述べ
てきた「共感重視」傾向がコメントから確認できるのか、また、「コミュニケーシ



